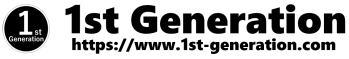5月14日から、ポレポレ東中野にて、映画『距ててて』が上映中。本作は、振付師・俳優の加藤紗希と脚本・俳優の豊島晴香の「点と」という創作ユニットが製作した初長編映画。写真家を目指すアコ(演・加藤)とフリーターのサン(演・豊島)を主人公とした、4章構成のオムニバス作品。
どのように映画美学校へ進み、どのように出会ったのか、二人にお話をうかがった前半に続き、後半は作品について、ご自身との比較などたっぷりとお話しいただきました。

■ 映画『距ててて』監督・加藤紗希、脚本・豊島晴香インタビュー(後編)
▼映画『距ててて』とお二人 ~お二人自身と演じるアコとサンについて~
-それぞれのキャラクターについて、“アコは几帳面でストイック、サンはだらしなく自由気まま。”と書かれています。
ご自身とそのキャラクターとは、似た部分がありますか?それとも、全く別なキャラクターでしょうか、そういった点についてお話をきかせていただけますか。
加藤紗希
今思うと、やはり自分に近いものではあるんじゃないかなと思っています。でも作り始めた当時はそんなことは考えていなくて、自分に近いものを演じたいとはあまり思っていないです。むしろ私は自分の“素”が見えることに対して、わりと怖さを感じるんです。
もちろんいただいた役や、自分で作り出す役に対しては、自分の心を使って理解をしたり、共感をして演じたいと思っていますが、作る上で自分と近いキャラクターであることは必要ないと思っています。
前作の『泥濘む』という短編作品があるんですが、そのときにやりたかった役が、私の場合“だらしない人”だったんです。なぜ“だらしない人”がやりたかったかというと、それまでオファーをいただいた役で、そういう役をもらったことがなかったからで。
結構“真面目な人”みたいな役をいただくことが多かったんです。実際に真面目で、しっかりしているふうに見られるし、そういう役をもらうことが多いんですけど、せっかく自分で作るんだったら、普段やらないような役がやりたいなっていうのがありました。もちろんだらしない部分もありますし。(笑)
その役があって、逆に『泥濘む』では豊島さんが演じた役は、周りからストレスを受けたりするっていう、真面目な役でした。そこが対比するような役ではあったんですけど、そういうものが一作目にあって、「じゃあ次にやるときは逆転したようなことがいいよね」ってなって、だらしないというか自由奔放なサンなんですけど、ベースとして最初に考え始めたところがありました。
豊島晴香
私からみても、加藤さんはしっかりした役や、大人っぽい役をよく振られていると思うんですけど、でも今回のアコはしっかりしていると見せかけて実はそうではない、っていう部分が重要で。どこか学級委員長気質で完璧主義のように見えるけど、実際色々なことが全然できていない。大人っぽいというよりはちょっと子供っぽいところがある役を加藤さんにやってもらったら可愛いだろうなと思いました。しっかりしたい自分とその理想からはみ出しまくってる現実のギャップに人間臭さを感じるというか。だから私は加藤さんがよく振られるような役を書いたとは思っていなくて、私たちの関係性だからこそ知っている、人間臭い加藤さんを役に落とし込みたいと思っていました。
加藤さんはやっぱり“スタイリッシュ”と見られがちだと思うんですけど、私はどちらかというとそういう人間臭いところに興味があるし、見てほしいと思います。
加藤紗希
“几帳面でストイック・自由奔放”っていうふうに書いてはあるんですけど、私は人間は多面性を持っていると、自分自身にもそう感じるんですよ。真面目な部分ももちろんあるし、なんか真面目すぎて、自分が嫌になることがよくあるんです。
でもそんな部分だけじゃないし、ものすごい適当な部分もあれば、自分で最悪やなって思うことも日常にあったりとかするんで、そうやっていろんな面を持っているのが人間だと思っているから、映画を観た時に、「この人はこうだったよね」っていうふうに単純に言語化できないようなキャラクターにしたいなと思っていました。キャラクターを言い表すときには、どうしても一つか二つの面にはなってしまうんですけど。いろんな面を持っている一人の人間であるっていうことに最終的になったらいいなっていうのは思っていますね。
豊島晴香
そういう役に対して、加藤さんが切ってくれた髪型だったり、選んだ服だったり、私はすごい嬉しかったです。役が立体的というか、生になった感じがして、それによって私もアコっていう存在のイメージが膨らみました。
「こういう家庭で育ったんじゃないかと思っている」といった話を聞いたときに、「そんなふうに考えて立ち上げてくれたんだ」みたいな、「なるほど!」といった説得力があったので、「アコってこういう人なんだ」って。その時はまだその先で書いていない章もあったのでかなりそのイメージに影響を受けました。
私は私で、やはり真面目でしっかりしている役、女社長とか振られがちで。特にその頃って、もうちょっと精神的に余裕がなくていろいろガチガチな時期だったので、かっちりかっちりした役をいつも振られていたんです。
サンって私の幼少期のエピソードをいろいろ盛り込んでいて、親宛の手紙とか郵便を自分の部屋に何も見ないで投げ込んでしまって、毎日のように怒られたり、部屋がすごい汚かったりとか、小さい頃実際にあった話なんです。
だけど大きくなるにつれて、そのままでは生きていけなかったっていうか。1回就職もしていて、ちゃんとしなきゃみたいな意識で今の私があるわけなんですけど、もしそういう“ちゃんとしなきゃ”が全部ないままで育っていたらこうなっていたかもしれないっていう、最初はそういうイメージで役を書いていました。ちょっとちゃらんぽらんな役をやってみたかったっていうのもあったんですよね。
だけどやっぱり、なんだかんだでサンは一緒に住んでいるアコの存在を気にしながら生きている人なんだなっていうのを演じながら感じました。少なくとも今の私が演じるとそうなってしまうなと。
これが人から与えられたサンっていう役だったら、もっとちゃらんぽらんで突き通したかもしれないんですけど、自分で書いた役で自分が演じるとなると、今の自分がどうしても反映されてしまうなと思いました。でも結果的に、加藤さんから多面性という言葉がありましたが、そういう人物造形に繋がったとも思っていて。私もすごい多面性は大切にしたいと思っているので、それで良かったとは思っています。

▼本作制作のきっかけ
-この話が例えば何かのエピソードから作られたのか、それともゼロから創られたものなのでしょうか。
加藤紗希
きっかけとしては、先ほど話に出た『泥濘む』という作品がPFFに2019年に入選して、映画祭でたくさんの人に観てもらえたことと、ものすごいいろんな感想をいただいたんですけれども、それがものすごく豊かなことだと感じました。その作品って『距ててて』と同じキャストが出演しているんです。
全員がアクターズコースの同期の方たちで、半年間一緒に講義を受けたし、同期の人たちと作品を作りたいなと思って、『泥濘む』をつくりました。でも仲間で作った一つの映像作品ではあるけど、映画と言えるのかどうかがあまりわからなかったっていうのが正直ありました。
それが、PFFに入選したことによって、いろんな人に観てもらえたし、自分たちが思ってもみないような感想が数多くもらえたんです。
そのことが今までの人生で経験していなかったような体験で、「なんて面白いんだこれは」と思ってものすごく感動しました。25分の短編でしたし、次は長編で同じキャストが出ているけど違う物語を生み出したいと思いました。
それが『距ててて』を作りたいきっかけだったんですよね。それをまたPFFに入選させたいというのを目標で作りました。やはり観てもらわないと。「映画は観てもらって映画になる」というのを友達から聞いていたんです。『泥濘む』を作る前に。本当にそれを感じて、その時に「観てもらう場所がなければ、映画にならないのかも」と思っていました。あとPFFって一次審査、二次審査を担当しているセレクションメンバーの方たちが感想を送ってくださるんです。落選していても入選していてもPFFは感想をくれるんです。それをまずもらいたいっていうのと、入選して、またみんなであそこに行きたいというのが目標としてありました。それで始まった企画ですね。
話の考え方としてはさっき言った『泥濘む』の中でやっていないような役柄。私たちは演じることを起点に、“人”と”場所”をベースに持っていて、その場所でこの人が何をするかとか、こういうキャラクターを演じてもらいたいとか、この人とこの人にこういう関係性のものをやってほしいっていうところから割と考え始めているのと、「次はこういうことがやりたい」といった私の中でのアイディアを豊島さんにポロポロと伝えて、プロットを考えて豊島さんが脚本にしてくれるっていう流れで作りました。
豊島晴香
もともとの話があったというよりはアイディアベースで使っている程度ですね。さっきの私の幼少期のエピソードも、話の流れ全体に生かされているというよりは、例えば郵便物を部屋に持ち込んでしまいがちっていうサンのキャラクターに反映されていたり。
あと、加藤さんのおじいちゃんの思い出というのが、映画に入れ込みたいアイディアとしてありました。二人で映画を作り始めるときは、アイディア出しをしつつ、プロットの方向性をしゃべる時間があって、それが要素になっていきますが、“元ネタがしっかりあります”っていうものではないんです。
加藤紗希
製作過程でどんどん入れてくみたいな感じだよね。
豊島晴香
そうだね。
▼4章立ての構成はいつ頃決まったか?
-4章立ての構成は最初から決まったのですか?
加藤紗希
それは豊島さんからのアイディアです。
豊島晴香
これは長編を撮りたいと言われたときに、「長編かぁ…」ってなって、まず自信がなかったんです。長編をどうやったら書けるのかもわかんないし、「ん~」と思いました。
コロナになる直前になんとなく出していた長編のプロットもあったんですけど、それがコロナだと若干、作るのが…一か所にたくさんの人がいっぱい集まる作り方のプロットだったっていうのと、内容的にもぶっ飛びすぎていて、難しいっていう回答が返ってきて、私はその時点で「やっぱり、考え直さなきゃいけないかぁ~」となったところで、オムニバスで1個1個が区切られるんだったら書けるかもと思いました。
私は締め切りを延ばしたい癖があるんですが、最初の考えでは1章書いたら1章撮る、といった進め方をすると思ったんです。ひとつを短く、頑張ったら、しばらく休めるだろうと。それでオムニバス形式を提案したら、ちょうどそのときに加藤さんが『レネットとミラベル/四つの冒険』というエリック・ロメールの映画を観ていて、そのタイミングで…
加藤紗希
オムニバスとあとは私達がメインのキャラクターであることが決まりました。
豊島晴香
「これを観て」ってすぐに言われて、ザ・シネマに入会して私も観て、「じゃぁ、それでいこう!」っていう感じになったんです。
でも結果的にはオムニバスだからといって、“一個書いて、一個撮る”ではなくて、ある程度書いてから撮り始めました。加藤さんからそうじゃないと撮り始められないという話があって。結果的に細かい締め切りが短期間にいっぱいあって、追いつめられる感じになっちゃいました(笑)。
ただ4章だけは、半分は3章を書いた時点で4章を考えた方が面白いんじゃないかという実験的な気持ちと、もう半分は最後の1個だけはどうしても締め切りを延ばしたいというよこしまな気持ちがあって(笑)。「4章はもうちょっと撮り進めた段階で考えたい」って加藤さんに提案しました。
結果、おおもとのプロットとしては数ヶ月前にはできていたんですけど、脚本として書き上がったのは、4章を撮影する数日前でした。
加藤紗希
前日とか前々日でしたね。
豊島晴香
4章は、私と加藤さんだけしかいなかったので。他の俳優さんがいたら負担が大きくなってしまうので難しいんですけど。
加藤紗希
他の俳優さんがいるので、撮り始める前に「まず3章まで書いて欲しい」って言ったんですよ。クランクインしているのに、自分の役がどうなるかわかんない状態で、現場だけ進んでいると怖いじゃないですか。だから参加してもらう手前、安心してやってほしいなっていうのもあって、豊島さんは大変だったと思うし、自分の思惑とは違う方向に進んでいったと思うんですけど。
豊島晴香
本当にしんどかった(苦笑)
加藤紗希
4章に関しては自分たちの出演だけだし、何とかなるでしょうっていうことと、そこまで私も追いつめたいわけじゃないので、豊島さんが追い詰められないようにしたいと思っていて、「だからそこは追々で~」みたいな(笑)
-撮影はいつ頃から、どのように行われたのでしょうか?
加藤紗希
季節が変わっていくような物語で、最初は夏から始まるんですけど、実は撮影時期が11月で。ひと月に1章ずつ撮っていくような感じで、1章につき、2,3日ずつで、撮影の現場は、ゆったりというか、なるべく日程を離して、皆さんにコロナ禍だったので状況を聞き、体調管理をしてもらいつつ、現場を作っていました。
豊島晴香
今思うと、2章を撮り終わったぐらいの時点で、なんとなく4章を書きたくなっていました。続きの物語を考えたくなってきていたんだと思います。
もともとPFFの締め切りが2021年の3月23日だったので、3章は1月、4章は2月というスケジュールで進めようとしていたのですが、コロナの影響で、結果的に3章と4章の撮影は2月末と3月頭といった感じでくっついてしまったんです。
元々予定していた1月に、3章をこれから撮ろうという段階で、なんとなくプロットを考えた記憶があって、やっぱり書きたい気持ち・物語の続きを考えたい気持ちが出てきていたのかなって改めて思います。
加藤紗希
演じていて繋がってきた部分もあったよね。回収じゃないけど、こう着地させるみたいなことだったり。
豊島晴香
加藤さんからおじいちゃんのエピソードを入れたいっていう話があって、それを4章に結びつけたいみたいなことは言われていたんですけど、「ぇ、難しくね?」と思いつつ、それをなんとかするために、全然先は見えていないけど、1章におじいちゃんというワードを宿題みたいな形で入れておいたんです。
「おじいちゃんにドラムを買ってもらってやっていた」といった台詞があって、でもその宿題を入れておくと、どう育てるかっていう感じで考えやすくもなるし、やりたいって言っていたことを無視しないでも済む。そんな感じでいろいろ散りばめていたものがまとまっていくのを感じたり、なんとなく方向性が決まっていきました…。ラストは最後まで決まらなかったですけどね。
▼お客様へのメッセージ
-それではお客様へのメッセージをお願いします。
加藤紗希
『距ててて』って、観る人によって全然視点が違ったり、気に入るポイントだったり疑問に思うポイントだったりが人によって違うんです。
それはPFFと、TAMA NEW WAVE、田辺・弁慶映画祭という三つの映画祭に参加して実感しました。
劇場公開って、映画祭よりもさらにいろんな方に観ていただける機会だと思うんですけど、そんなたくさんの方が観ていただいた一つ一つの異なる感想を聞くのが楽しみで。観終わっても、「わかんない!」みたいな感じになるかもしれないんですけど(笑)、それでもかまわないですし、豊かな経験になればいいなと思っています。
あとは、作品を観たときって、手放しに楽しめるという良さと、観た後に考えるみたいな良さがあると思うんですけど、自分で作るときは何も考えずに観られるっていうよりは、思考を動かしてみる方が私は楽しいなと思うので、そういう作品になっていたらいいなと思います。
豊島晴香
宣伝活動を通して、インタビューの機会をいただけて、出演俳優の人たちとスタッフチームとのインタビューをしていただいたんですけど、改めて、全員野球じゃないですけど、1人1人が作り手として立って、参加してくれたからこそできたって作品。「呼ばれて聞きました」じゃなくて、自分が作るっていう言葉が正しいかわからないですけど、でも「言われたことをやる」ではない関わり方をしてくれたからこそ、できた作品なんだろうなと思います。
私たちのスタンスとしては、一人一人、俳優もスタッフさんものびのびと自分のやりたいことを自由にやれる環境を構築するのが、豊かな作品につながると信じているところがあって。もしかしたら、バラバラに見えるものもあるのかもしれないんですけど、そこも豊かさであると私達は思っています。
そういうことを感じてもらえたらすごく嬉しいし、つくる楽しさが伝わって「自分も作れるかも」って思う人がいてくれたらいいなって思います。映画じゃなくても全然いい気がしていて、それぞれの「こうやりたい」というのをお互いに面白がりながら集団で創作する、ということに興味を持ってくれる人がいたら私としてはすごく嬉しいなと思います。

【前編】
映画『距ててて』加藤紗希監督、脚本・豊島晴香。映画美学校への道。二人の最悪の出会いとは
■ 作品情報
映画『距(へだ)ててて』
監督:加藤紗希
脚本:豊島晴香
出演:加藤紗希/豊島晴香/釜口恵太/神田朱未/髙羽快/本荘澪/湯川紋子
撮影:河本洋介
録音・音響:三村一馬
照明:西野正浩
音楽:スカンク/SKANK
宣伝美術:一野篤
宣伝協力:天野龍太郎
製作:点と
(2021年/日本/フィクション/78分)
最新情報は公式Twitter(https://twitter.com/hedatetete)およびInstagram(https://www.instagram.com/hedatetete/)で随時発信。
5月14日(土)、東京・ポレポレ東中野ほか全国順次公開