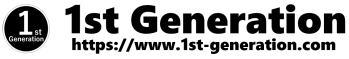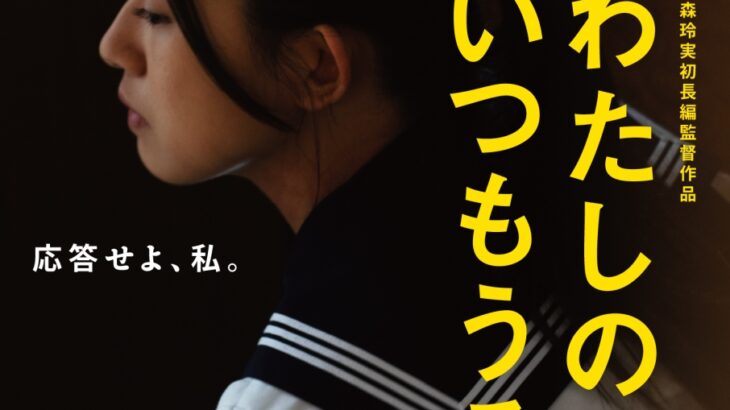第55回⽇本映画監督協会新⼈賞にノミネートされ、国際的に注⽬が集まる神保慶政監督作品の特集上映『⽣活の中の映画』が、6⽉28⽇(⾦)より下北沢K2を⽪切りに全国順次公開することが決定。特集上映の決定にあわせて、予告編とメインビジュアルも解禁。映画が持つ「特別さ」を彩り鮮やかに表現し、「 “⽣活”と“映画”の境界線が溶けていく」というコンセプトをビジュアルと予告編で表現している。

■ 神保慶政監督オフィシャルインタビュー
ー監督を志したきっかけについて教えてください
大前提としてまず、「映画が好き」という気持ちがないと映画業には携われないかと思います。僕の世代は小学校の中高学年ぐらいで『スター・ウォーズ』の特別篇というのが公開された世代ですが、その辺の時期から週末しばしば映画に連れて行ってもらうような日常を送っていました。中学・高校になったらTSUTAYAの「その他」という棚の作品を片っ端から観ていくというような形で国内外様々な映画に触れました。それでもまだ「映画を作る側になる」という考えには至っていませんでした。就職活動の時に配給会社とか映画関連の会社を受けたとき、いい線まで行くのですが、選考に一社も通過しませんでした。その時、結果としては残念だったのですが、ものすごく腑に落ちました。というのも、自分は映画を広める側とかではなく、作る側であるという自覚がそこで芽生えたからです。そのような解釈のしかたには、大学のバンドサークルである程度「表現とは何か」について考えていたこと、コピーバンドで飽きてオリジナルバンドを始めたという一歩が効いていたかと思います。その後はもう、進むだけでした。だから「志」を持ち始めた瞬間というのは、正直どこなのかわかりません。でも一番の転換点は、就活の時の気付きでしょうね。
ー学生時代の将来の夢は?
正直なところ「将来の夢」というのは全くありませんでした。これもやっぱり時代だと思うのですが、夢を持たなければいけない、自分とは何かわかっていなければいけないというようなプレッシャーが大人社会にあって、それが子どもにも伝播していたように思います。それが無いのが悩みの1つでもありました。「その質問にちゃんと答えられなければいけない」というようなプレッシャーがあったように思います。こういったことは、今回途中状態で上映するドキュメンタリー『冒険―会いたい人に会いにゆく』に多く収録されているので、いまだにそういった風潮は存在し続けていると思います。劇中の言い回しを借りると「何者かにならなければいけない」という、漠然とした、でもすごく重い強迫観念です。今回の上映のアプローチを考える上のキーワードのひとつは、バナキュラー(vernacular)です。自分の活動について建築家の遠藤幹子さんに話したときに、この言葉を教えてもらいました。土着的・自然発生的などと訳される建築用語です。例えば合掌造りという建物がありますが、それはその土地の人が「合掌造の建物を作ろう」としたわけではなくて、気候や風土から割り出される最適解を模索した結果のものに「合掌造」と名前が付いた。そういう順番で考えることがバナキュラーなアプローチです。僕にとって「夢」というのも、最初から持つようなものではなく、「コツコツ積み上げて行ったら夢になっていた(気づいたときにはもう見れないけど)」みたいなものだと思っています。
ー映画作りを始めるまでのキャリアについて教えてください
西遊旅行という秘境専門の旅行会社に勤めていました。「秘境旅行のパイオニア」というキャッチフレーズが付くような、昨年(2023年)で創業50周年を迎えたとても専門性のある会社です。いまだに「旅と映画」というワールド映画コラムを書かせてもらっています。当時は1年目が手配、2年目からは南アジア・チベット文化圏ツアーの営業を担当していました。いわゆるインディペンデント映画のような「最初から最後まで全て自分たちでやる」会社でしたので、企画・見積もり・手配・営業・添乗・販促物の制作まで携わることができました。映画制作の事務作業的なことや、監督業の基本は実は旅行業から学びました。特に添乗員のやることというのは、ほぼ映画監督のやることと同じだと考えています。「スタッフ・キャストを良い旅に連れて行く」というような感じが、僕の監督スタイルの基本になっています。なので時々監督をしながら、食事の場所とか移動の所要時間の読みとかがとても気になったりします。本来それは助監督とか制作とかがやる仕事なんですけどね。

ーそこから映画業界を志したきっかけは?
僕はこの「志したきっかけ」というのがあまりない人間なのだなということを、質問に答えながら感じますね。それでも思い返すと、先述した西遊旅行で「本気で何かが好きな人」の姿に触れたということがあるかと思います。僕もそれなりに秘境と呼ばれる場所の文化や、その場所をどう見てもらうかという表現に興味はありましたが、「本当に本当に興味がある人」にはかなわないという経験をしました。その自分の感覚を通して「自分がこれぐらいのめり込めるというは映画だ」という潜在化の考えが掘り起こされたような気がします。なので、西遊旅行の方々のおかげですね。
ー映像・映画制作の会社に入らなかった理由は?
この質問は初めて聞かれました。なんでなのでしょうね。おそらく、映画をやり始めるまでに若干の遠回りをしたので、1番近道で自分の作品を作りたいなと思ったからでしょうね。面接にすら行かなかったです。「監督をやりたい」ということをはっきりしていました。他の誰かの制作とか助監督とか、あまり向いてないんですよね。自分の映画のための助監督的作業や事務作業だったらすごく細かくできるのですが、それを他の人のためになかなか発揮できないんです。すごく自分勝手ですね。
ー尊敬する映画監督、作品は?
たくさんいますが、フランスとイランの映画に強い影響を受けてきました。フランスでは例えばジャン=リュック・ゴダール。特に好きなのは『女と男のいる舗道』です。『0ライン―赤道の上で』の主人公・ナナの名前はここから採っていますし、ナナが哲学者と即興をまじえつつ会話する有名なシーンは『冒険―会いたい人に会いにゆく』の撮影スタイルのベースになっています。アラン・レネの『ヒロシマ・モナムール』も繰り返し観ています。
イランはたくさんいすぎて書ききれません。日本ではあまり観る機会がないかと思いますが、マルズィエ・メシュキニの『私が女になった日』という作品が最初のきっかけです。イギリスのArtificial Eyeというソフトシリーズで鑑賞しました。
日本は小津・黒澤・溝口・成瀬・清水、鈴木清順、寺山修司などなど。小栗康平の『埋もれ木』にも影響を受けました。
直接マスタークラスで指導を受けたこともあるトラン・アン・ユン監督、アピチャッポン・ウィーラセタクン監督も尊敬してます。。
ー子育てがきっかけで福岡に移住されてますが、子育ての経験が映画作りに与える影響はありますか?
子育てをしなくても、ファミリー映画とか子育ての映画は撮れるかと思うのですが、やはり子育ての経験は色々と映画作りに影響しています。僕はどちらかと言うと、子育てそのものというよりも「そうじゃなかった人生」というものを強く意識するようになりました。つまり、「子どもができる」「2人目の子どもが産まれる」という道を進むなかで、「子どもができない」「2人目はよしておく」というような、自分が経ることのなかった人生はどういうものだったのだろうと考えるようになったということです。この観点は例えば、様々な理由で子どもがいない大人が、町にいる子どもたちとどう関わるかと言うような形でまちづくりや映画の表現につながってきます。子育ての映画を撮るとして、そこに子どもを自分で育てている人しか出てこなかったら、すごく偏った話になりますよね。映画というのは総合芸術なはずなので、一面的・表層的ではダメで、多面的・多層的であるべきだと思います。
中で映画監督が何をするかというと、選択と決断です。建築や街づくりにおいても、民主的なプロセスを経るならば、誰でも希望や考えを言うことはできるでしょう。でも、それにゴーサインを出したり、選択したりするのは、建築家や街づくりの主たるポジションの人たちです。そしてそうと決めたら、選択した事項を表現することに労力や資本を注ぎ、かつ、全体としてバランスがとられているようにする。これがすごく似ているなと思います。
ー海外での制作や国際共同制作が多い理由は? 合作についてはもともと戦略的に考えていましたか?
前の質問と少しつながりますが、日本を超えての映画作りにおける事務作業や手配作業が、自分1人でできてしまうというのはかなり珍しいのではと思います。それがプロの制作ばりにできてしまうと言うのは、紛れもなく旅行会社の経験のおかげだと思います。
戦略性は多少はありました。例えば『せんそうはしらない』という作品はイランの映画祭に出したいと企画当初から思ってつくって、実際イランの映画祭で上映されました。その後『0ライン―赤道の上』でのオファーがイランから来ました。その結果、合作になりました。こういう順番なので「合作を作ろう」「合作の方が面白いよね」というような意図から作品は生まれていません。これもまたバナキュラーなアプローチですが、興味関心にしたがって進んでいた結果、国際共同制作になったり、外国ロケが入ってくると言う順番です。
ーベルリナーレ・タレンツや映画祭との向き合い方について教えてください。
ベルリナーレ・タレンツは、ベルリン映画祭が主催している人材育成事業で、世界約100カ国位から200人ほどが集結します。僕の年は日本人が僕一人で、四年応募し続けて念願かなって2021年に参加しました。しかし残念ながら僕の年はコロナ禍だったので、オンライン開催で現地に行けませんでした。通常は現地で世界中から新進気鋭のフィルムメーカーたちが、一堂に介する場が毎年取り持たれています。監督だけではなくて、各技術ポストや俳優も応募できますが、特にユニークなのはオーディエンス・デザイナーというポストが2020年頃から新設されたことです。映画が今後どのように存続可能かという実践的・リアリスティックなことを話し合う場なため、このベルリナーレ・タレンツに僕の考え方が評価されたというのは、とても自信になりました。
修了生だけがアクセスできる場もあります。そして何よりものすごくネットワークが広く、例えばホンジュラスのフィルムメーカーにアクセスしたいという場合に、ベルリナーレ・タレンツの人材ネットワークを調べると素早くアクセスできます。僕も時々ベルリナーレタレンツの修了生で「今度日本に行くから会えないか」と、突然見知らぬ誰かからメールが来ることがあります。その輪の中に入れていると言うのはとてもうれしいですし、いつかベルリン映画祭で映画祭を上映することができればなぁ、と目標にする映画祭もできました。
その他にも僕は主に企画開発の段階において、いろんな映画祭のお世話になってきました。プチョン国際ファンタスティック映画祭のファンタスティック・フィルムスクール、Asian Pacific Screen AwardのAsian Pacific Award、ナント三大陸映画祭のProduire au Sud、ベルリナーレ・タレンツの暖簾分け的な東京フィルメックスのタレンツ・トーキョー、ベトナムのオータム・ミーティング。これらの助成枠組みやワークショップに参加して圧倒的に人脈や経験は広がりました。
ードキュメンタリーとフィクションを織り交ぜた映画作りをしているのでしょうか?
専門的に話し始めると、この話はものすごく長くなるので、なるべく簡潔にお答えしたいと思います。例えば今回の上映の中で1番フィクション度合いが高いのは『せんそうはしらない』、ドキュメンタリー度合いが高いのは『冒険―会いたい人に会いにゆく』です。前者はフィクションほぼ100%。これは、脚本通りと言うことを意味します。後者はドキュメンタリー85%ぐらい、フィクション15%ぐらいです。フィクションの部分は、主人公の2人が以前の対話の録音を聞いているとか、会いたい人に会いに行っているという行動とか、会いたい相手というのは僕が指示・準備しています。その他は何も台本がなく、ありのままに話してもらっていて、結末もまだわかりません。僕が指示・準備している部分がフィクション、ありのままの箇所がドキュメンタリーというお考えいただければと思います。これは「混ぜよう」と思って混ぜているわけではなく、最適手段を模索する中で自ずと混ざっていくと言う感じです。被写体の皆さんが迷いなく違和感なくカメラの前にいれるように「今から撮るのはフィクションです」「ここからはありのままで大丈夫です」「この後はもう撮りません」と、なるべく白黒ははっきりさせます。
なぜ混ぜる必要があるのかということですが、僕の今時点での映画づくりと言うのは、リアリズムの優先順位が高いと言うことだと思います。それはつまり「本当らしさ」「確からしさ」が、話されている内容そのものよりも重視されると言うことです。
例えばある企業のインタビュー映像を撮るとしましょう。ある人はスラスラと言い間違えなく答えているけれど、あまり感情はこもっていない。一方別の人は、詰まったり、言い直したり、言う前にうーーーんと数十秒考え込んでから話し始めるけれども、自分で言葉を紡いでいる感じがする。僕は後者のような性質の言葉が興味関心対象です。「ちゃんと言える」ということはどうでもよくて、心の芯を通過してきた言葉・表情・行動に出会いたいということです。
ー映画を作りながら企業参画も行っていますが、相互に影響することはありますか?
現代社会は「答えなき時代」とよく言われます。VUCAという言葉も最近はありますよね。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)。これはビジネスとかにとっては課題・障壁なのかもしれませんが、文化芸術領域の人間にとって、実はさほど問題ではありません。なので、今の時代ほど企業やビジネス領域に、映画制作者等の芸術領域の人が役立てる時代と言うのもないのではないかと思います。
今回上映する作品の中に『Workcation』という作品があります。ワーケーションって実際どういうものなのかというプロモーションも兼ねて制作された映画です。自分でワーケーションを体験しながら準備しましたが、僕にとっては「いつも通り」な感じでした。つまり、観察したことや感じたことを、自分の作品や行動に活かすという時間を過ごすということです。皆そうやって生きてるんだと思っていましたが、実はそれなりにそういった「咀嚼能力」「解釈」みたいなものは特殊技能であったり練習が必要だという事を、他の人の反応から知りました。
今回の特集上映は同業者・映画制作者に向けて訴えかけているものもあると思います。それは「上映される映画」「観る映画」だけが映画だと考えていると、この先映画業界はどうなってしまうのだろうかという疑問符です。映画の定義をグワッと広げて「企業の会議室のやりとりの中にも、目には見えない映画的瞬間がバンバン立ち現れている」とより多くの人が認識するようになった時、巡り巡って「観る映画」の集客も増えるのではないかというのが僕の仮説です。企業参画したいと思って企業参画しているわけではなく、現代的な文脈において「映画というのは何か?」ということを突き詰めて考えていったときに、企業参画することになったと思っています。
ー次の10年に向けての意気込みは?
とにかく作り続けたいという一言につきます。今までは、最初の長編作品『僕はもうすぐ十一歳になる。』を除いては、オファーを受けていわば頼まれ仕事で作ってきました。自分で自主的に作りはじめて実現しているのが『冒険―会いたい人に会いにゆく』です。やはり、何かキーワードが決まっていたり場所が決まったりしているのも良いのですが、完全に自由で、任せきっていただくのが1番良い効果が出るというのを作りながら感じています。
当然、どういうものができるのかわからないという不安は周囲の人にはあるかと思いまして、今ドキュメンタリーを一緒に作ってもらっている皆さんは「これってどうなるんですか?」と聞かれて「今の段階ではここまでわかりますが、これ以降はわかりませんし、場合によってはわかってる部分もガラッと変わるかもしれません」などという説明を何回も何回も聞いてもらうことになって、本当に申し訳ないなと思っているのですが、上映用に編集したものには結果的にものすごく満足してもらえました。そんな自由な制作というのはなかなかないとは思うのですが、完全に自由に作ってくれと何も指示内容がなくても、僕は作れる人間です。
福岡県の大牟田というところに「ともだちや絵本美術館」というところがあるのですが、そこで詩の特集があるときに行きまして、僕の方が子どもよりも夢中になって詩を書いていました。何パターンかのお題がある中に「自由に書いてください」という、真っ白なキャンバスを渡されたかのようなのがあったとき、通りかかる大人は「あーこういうの私の1番苦手なやつ」と、子どもは「ねえ何書けばいいの?」というリアクションが多かったです。僕はその真っ白なキャンバス状態が1番盛り上がります。別にみんなそれが書けるようになってほしいとかそういうことではないのですが、僕は積極的にそういうのは請け負っていきたいと思います。福岡市の東区の九州大学跡地で、完全に更地の状態からこれから都市計画が進んでいくのですが、今回の上映の中で実験しているように、映画の言語というものをまちづくり等の違うものに翻訳すると言うことも、今後10年でより形にしていきたいと思います。

▼予告編
特集上映の決定にあわせて、予告編とメインビジュアルも解禁。映画が持つ「特別さ」を彩り鮮やかに表現し、「 “⽣活”と“映画”の境界線が溶けていく」というコンセプトをビジュアルと予告編で表現。
神保慶政監督
‒プロフィール‒
東京都出⾝、2016年より子育てきっかけで福岡市在。
フィクション⻑編『僕はもうすぐ⼗⼀歳になる。』で監督キャリアをスタートさせ、⽇本映画監督協会2014年度新⼈監督賞にノミネート。
短編『せんそうはしらない』など過去作は世界各地で上映され、韓国・釜⼭のスタッフ・キャストと制作した短編『憧れ』(2017年)からは国際共同制作を積極的に開始。
ベルリン国際映画祭「ベルリナーレ・タレンツ」、東京フィルメックス・東京都主催「タレンツ・トーキョー」など、映画祭の⼈材部⾨に数多く選出。
活動はアジアフォーカス福岡国際映画祭プログラマー、福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会ブログラム部会委員、英⽇字幕翻訳、書評・映画評執筆など⽂化芸術⽅⾯だけではなく、ガス会社・シェアオフィス等への企業参画など、映画を現象に応⽤・転化させことも「映画」と呼びつつ幅広く活動中。
特集上映情報
神保慶政監督 特集上映 『⽣活の中の映画』プログラム
○プログラム『⾃分を⽣きる』“⾃分らしい豊かな⽣き⽅”を⾒つけるヒントが詰まった作品集
『Workcation』 『冒険―会いたい⼈に会いにゆく』 『憧れ』75min/カラー/ 2ch/ ドラマ&ドキュメンタリー
◯プログラム『旅を⽣きる 』”⼈⽣の冒険”を通して、新たな視点で世界を⾒つめる作品集
『せんそうはしらない』『0ライン―⾚道の上で』96min/カラー/ 2ch/ ドラマ
◯プログラム『⼦どもを⽣きる 』“素朴な疑問と発⾒”から、新たなエネルギーに出会う作品集
★⼦どもたちにもおすすめのプログラム
『えんえんと、えんえんと』『僕はもうすぐ⼗⼀歳になる。』93min/カラー/ 2ch/ ドラマ
スタッフ
監督:神保慶政
コピーライター:イリエナナコ 宣伝美術:鈴⽊規⼦
予告編: 堀合豪⼈(Mogross) 配給・宣伝:夢何⽣ 宣伝協⼒:⽮部紗耶⾹
公式Web: https://seikatsu-eiga.studio.site
神保慶政監督特集上映企画『⽣活の中の映画』
2024 年6⽉28⽇(⾦)より下北沢K2ほか全国順次公開